環境コラム
群馬大学 粕谷健一 教授インタビュー
海洋ゴミ問題を解決に導く「生分解性プラスチック」研究開発の今。
そして、これから

群馬大学 粕谷健一 教授
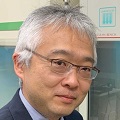
群馬大学 大学院理工学府分子科学部門 教授(学長特別補佐)
(兼任)食健康科学教育研究センター 食品開発ユニット 教授(センター長)
なぜプラスチックに「生分解性」機能が必要か?
粕谷先生は分子科学領域がご専門で、環境汚染物質を無毒化する微生物や、生分解性プラスチックについて研究をなさっています。今回は包装材と海洋プラスチックゴミの問題についてお話を聞かせてください。
粕谷健一教授(以下、敬称略):2016年に、サーキュラーエコノミーを推進しているエレン・マッカーサー財団(英)が、2050年になると海洋プラスチックゴミが魚の量を超えるという研究結果を発表しました(※)。それ以来、いわゆる“海ゴミ”の問題が世界的にクローズアップされるようになっています。最新の報告では、例えば太平洋の場合、海流の関係などで主に2ヶ所に海ゴミが多く溜まっています。その内の1カ所を調べてみると、表面には特に漁網が多く、プラスチックゴミの約半分が大きなプラスチックでした。
しかし、深刻なのは海底に沈んでいるゴミだと感じています。最新の研究では、深海底にいけばいくほど、パッケージングの材料として使われたプラスチックゴミが多くなることがわかってきました。水深3,000m以下では実に9割がパッケージング系のゴミだったのです。
実は日本でも回収に向けた取り組みは始まっています。しかし、深海からのゴミ回収は現実的に考えてかなりハードルが高く、このままだと今後も、海底にゴミが蓄積していくことになるでしょう。そのため2016年頃から国連をはじめとする専門機関などが、パッケージにプラスチックを使わないよう、非常に強い論調で呼びかけをはじめました。
※)"The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics", 2016/1
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
しかし昨年から続く新型コロナウィルスの問題によって、衛生を守る観点から、パッケージが果たしてきた役割が見直されています。今の状況から単純にプラスチック使用量を削減するのには、どうしても限界があると思います(※)。
※)Covid19 and Food safety, WHO and FAO, 7, Apr, 2020
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
そこで注目されているのが、生分解性プラスチックをはじめとする新しい素材ですね。
粕谷:そうですね。もちろん、生分解性の素材であろうとなかろうと、自然の中に流れ出ていかないような形で使うことが第一目標です。最近の研究では、地上で環境流出したプラスチックの約6割が、海洋までたどり着いてしまうと推定されていますから。ただ日本の現状をみてみると、海洋プラスチックゴミの大半は、意図せず流出してしまったものが多いのも事実です。
意図せずにというのは、具体的にどういったことでしょうか。
粕谷:あくまで一つの例ですが、東日本大震災が発生した1年後、仙台を訪れた私は愕然としました。津波で流されてしまったさまざまな物の中に、かなりのプラスチック製品が含まれていたためです。リサイクルが進んでいたとしても、自然災害によって大量に環境流出してしまうことがある。特に漁具や農業用途のものなどは、その危険性が高いです。だからこそ、生分解を一つの機能としてプラスチック素材に組み込むことが重要であると考えています。
"分解スイッチ"をもつ、日本型の新しい資材を目指して
今、粕谷先生が研究開発されている生分解性プラスチックとは、どのようなものなのでしょうか。改めてお聞かせください。
粕谷:簡単にいうと、これまで通りにプラスチックとして使用でき、海洋に流出してしまったり、海洋で使用中に誤って流出させてしまった際にすぐ分解が始まる素材です。いわば“分解スイッチ”を備えたような生分解性プラスチックですね(※)。一方で、一旦深海底に沈んでしまったプラスチックは、分解するために非常に長い時間を要することがわかっています。ある研究によると、海底に到達したポリエチレンは数百年、ポリプロピレンは数千年もの間、そこに残り続けると推定されています。これは、生分解性プラスチックであったとしても、深海底では同じように分解に時間がかかることを意味しているかもしれません。
そもそも深海底は生物活性が著しく低く、海中や海表面とはバイオーム(生物群系)が大きく異なります。そこにどんな生物がいて、どのような特性をもっているのか——現状ではまだまだわかっていないことが多く、これを科学的に正しく理解し、海洋で速やかに生分解する、「海洋生分解性プラスチック」の誕生までには、もう少し時間が必要になると思います。
※)NEDOムーンショット型研究開発事業 生分解開始スイッチ機能を有する海洋分解性プラスチックの研究開発
https://www.nedo.go.jp/content/100923469.pdf
一部ではプラスチックから紙のパッケージへの回帰が起きていますが、それについてはどうお考えですか?
粕谷:一つの考え方として、決して間違ってはいないと思います。できる部分はそうしていけばいい。ただ紙のパッケージが必ずしも環境にやさしいとは限りませんし、衛生面で問題が出てくるケースもあります。それに、外側のパッケージが紙で生分解性にすぐれていたとしても、中がポリエチレンでコーティングされていたり、インクが使われていたりしたらもうアウトです。だから生分解性を兼ね備えたパッケージの設計は、現実問題としてそんなに簡単なことではないのです。プラスチックを紙に変えれば済む話ではありません。
現在、生分解性プラスチックに関する日本の研究はどのくらい進んでいるのでしょうか?
粕谷:日本では2016年以降、環境省・経産省が中心となり、生分解性プラスチックの開発を含めた先進分野の研究を進めています。日本には非常にレベルの高い中堅メーカーが多いので、日本型の新しい資材を産み出そうとしている。これは現状、欧米にはみられない動きです。
その研究内容を社会実装していくには、まだまだ長い時間が必要になるでしょう。しかし今後、海洋でも生分解する材料の開発は絶対必要になるはずです。私たちは、5〜10年後を見据えて、何かしら社会に寄与することを目標に掲げて研究開発を進めています。
今回は、群馬大学の粕谷健一 教授から、特に最近ニュースで取り上げられる機会の多い、海洋プラスチックゴミについて、パッケージングの視点やその解決につながると期待されている生分解性プラスチックの話など、ご研究のテーマから最新の動向についてお話をいただきました。
次回は日本化学工業協会 技術部部長の野田浩二様から、ゴミを含めた資源の循環利用やCO2の削減などを、政府と協力してどのように促進していくのかという未来のお話をいただく予定です。どうぞお楽しみに!
(2020年8月インタビュー)